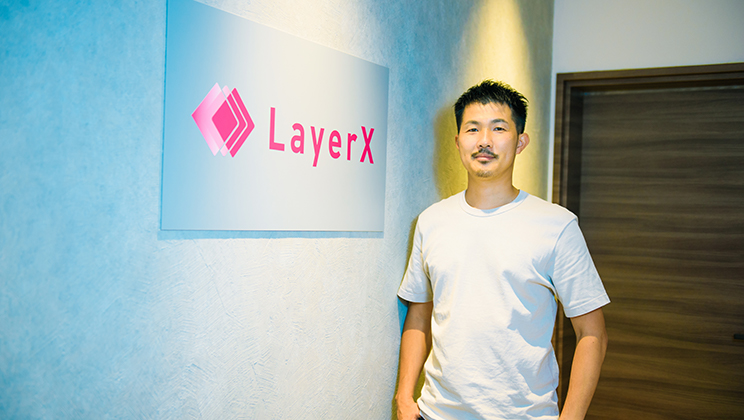衣料品問屋の街でチャレンジを続ける4代目。クリエイティブ×コミュニティで家業を更新する。
衣料品問屋の街でチャレンジを続ける4代目。クリエイティブ×コミュニティで家業を更新する。

日本橋エリアの北部に位置する日本橋横山町、日本橋馬喰町は、古くから衣料・雑貨関連の問屋が軒を連ねる繊維問屋街として知られています。武田悠太さんは、この地で創業した衣料品問屋「丸太屋」の4代目として生まれ、幼い頃から後継ぎを約束された人生を歩んできました。大学卒業後、コンサルティング会社勤務を経て、30歳を機に丸太屋の子会社再生を自ら買って出た武田さんは、従来の問屋事業にとどまらず、シェアオフィスの運営やホテル経営などこの街を拠点に次々と事業を広げています。クリエイティブ、ファッション、コミュニティをキーワードに精力的な活動を続ける街のキーパーソンにお話を伺いました。
後継ぎを宿命付けられた人生。
—まずは、武田さんのバックグラウンドから聞かせてください。
この日本橋横山町という地域は、古くから大阪の船場と並ぶ衣料品問屋の集積地なのですが、僕はこの地で70年近く続いている丸太屋という問屋の4代目として生まれました。創業者は僕の曾祖母なのですが、その下の祖母がひとりっ子で、大阪で医者をしていた祖父と結婚をしたこともあり、曾祖母の後は番頭さんが会社を回していたそうです。さらにその下の世代も3姉妹で、次女だった僕の母が東京に移り、婿養子として家に入った父が、3代目を継いだんですね。そして、僕が長男として生まれ、しかもその下が女の子2人だったこともあり、初めての男の子だった僕には、家を継ぐことが宿命付けられていたんです。
—家業を継ぐということに対して、反発心などはなかったのですか?
物心ついた頃から、自分が家を継ぐのだろうと思っていましたが、やはり納得できないところもあって、思春期には反発心を強く持っていましたね。そうした思いを抱えながら生きてきたのですが、社会人になる前には自分が後を継ぐということに意義を見出して納得したいという思いがありました。そして、バックパッカーとして世界中を回ったりする中で、自分の好きなことをする人生ではないかもしれないけど、やるべきことをする人生もそれに劣るわけではないと自分の中で強く納得することができ、そこからは前向きに考えられるようになりました。

父が経営する丸太屋の子会社「LOGS」の代表を務める武田悠太さん
—大学卒業後、すぐに家業に関わるようになったのですか?
いえ、アクセンチュアに入ってしばらくコンサルの仕事をしていました。ただ、これもゆくゆくは家を継ぐという前提のもとで選んだ仕事でしたし、大学にしても、社長になるなら慶応大学の経済学部が良いだろうと考えて進学しました。本社の丸太屋はいまも父が経営していますが、自分が30歳になった時に、父がニューカネノというすぐそばにあった衣料品問屋をビルごと買収し、その再生を僕が担うことになり、現在に至っています。
現状への危機感から生まれた2つの新事業。
—会社の再生にあたって、どんなことに取り組んだのですか?
これまで衣料品問屋の主な仕事は、ローカルの商店街にあるような小売店に洋服を卸すことでしたが、いまでは大手量販店と取引をしないと厳しい状況になっています。そこでまず僕らが取り組んだのは、強い商材をつくるために、当時アメリカで流行していた「ニューハッタン」という帽子ブランドと交渉し、日本の代理店になることでした。さらに、デザイナーやクリエイターを巻き込んでいくことをテーマに、自分たちの唯一の武器とも言える物件を使ってシェアオフィスの運営を始めたんです。

LOGSが日本の正規代理店となっているニューヨーク生まれの帽子ブランド「ニューハッタン」。さまざまなブランドやショップとコラボレートして、日本でも瞬く間に大人気ブランドになった
—強い商材をつくるというのはわかりやすいのですが、一方でクリエイターを巻き込むことにはどんな意図があったのですか?
問屋という立場からこれからの流通を考えた時に、クリエイティブとコミュニティがキーワードになると思ったんです。これまでは、生産、卸売、小売、つまり川上から川下までさまざまなプレイヤーがマーケットを介して商品を取引していたのですが、今後はクリエイティブとコミュニティが一体化していくことで、マーケットを介在しないやり取りが増えてくるんじゃないかと。
—ここで言うコミュニティとは、どんなものなのでしょうか?
同じ趣向性を持った人たちのことです。例えば、ONE OK ROCKのファンが関連グッズにお金を使うように、クリエイターを中心としたコミュニティが形成され、流通もその中で成立していく。こうしたマーケットを介さない流通が広がっていくと、問屋という川中の存在は不要になります。そういう危機感から、クリエイティブとコミュニティをつなげていくということを自らしていこうと考えるようになったんです。歴史を遡れば、刀鍛冶や陶芸家、料理人など、昔から良いものをつくる人の周りにはコミュニティがあり、この刀が欲しい人はこの茶器も好きという趣向の共通性もあったはず。もともと一体化していたクリエイティブとコミュニティが、この100年~200年の間の経済モデルの変化によって崩壊したということだと思うんです。
—シェアオフィスはどんな形で運営しているのですか?
co-labという都内各地にあるシェアオフィスのフランチャイズとしてスタートし、ノウハウを提供して頂いた後に、現在は自社で運営にあたっています。立ち上げ当初は、都内の他のco-labに立地条件では勝てないので、学校などを誘致して人の流れをつくれないかと考え、ネット検索でその存在を知ったファッションデザイナーの山縣良和さんにコンタクトを取ったんです。そして、彼が運営している「ここのがっこう」というファッションスクールをこの場所でやることになり、シェアオフィスにもファッションに関わるクリエイターや企業が集まるようになりました。


自社ビルの4〜6Fスペースで運営しているシェアオフィス。ビルの1〜3Fまでは祖業であるアパレル小物の現金問屋「ニューカネノ」になっている
ファッションとは、「好き」を発信すること。
—武田さんにとってファッションとはどんなものですか?
僕がファッションに携わっているのは、たまたま実家が衣料品問屋だったからです。アクセンチュアにいた時はヘルスケアを担当していたのですが、命を扱うお医者さんたちというのは、強い正義感や使命感を持っています。それに比べて、ファッションのファの字も知らないまま入ったこの世界では、カッコ良いか悪いか、売れるか売れないかという2軸ですべてが判断されているように感じました。マスメディアが機能していた時代ならまだしも、これだけ価値観が多様化している中で、個人の主観による判断で人を動員することは難しいし、一方で儲かる/儲からないの判断軸であれば、正直衣服よりも稼げるものはたくさんあるわけです(笑)。ニューハッタンが成功して会社が軌道に乗り、後を継ぐということも見えてくると、今度は「なぜ自分はファッションをやるのか?」という壁にぶつかってしまったんです。

日本橋横山町から程近い東日本橋にある丸太屋の本社ビル。現在は卸業の他に、ホテル経営や不動産業なども手がけている
—その壁をどのように乗り越えていったのですか?
ファッションの世界には、海外のラグジュアリーブランドから、そのエッセンスを取り入れた商品を安価で売るマス向けのブランドまでヒエラルキーがつくられているし、飲食店などにしても口コミサイトなどで序列が付けられていますよね。このヒエラルキーの下では、一部のお金持ちはラグジュアリーブランドを買ったり、高級レストランに行けますが、そうではない人たちは均質化されたものを消費させられるという二極化が起こってしまい、それはとてもつまらない世の中だと思うんですね。でも、もし1万円と100円のものがあった時に、100円のものを自分が好きで選んだと言い切れるなら、その選択は誰からもバカにされるものではない。いま、巷で多様性が謳われていることも、グローバル資本主義によって生まれたヒエラルキーや絶対的価値観の下では幸せになれないとみんなが気づき始めたからで、その時に「好き」「嫌い」をつくることができるファッションというのは、オルタナティブな考え方を提示できるのではないかと思うようになったんです。
—そういう意味では、武田さんにとってのファッションというのは洋服などのモノに限らないのですね。
そう考えられるようになってから、色々な事業を始めたんです。そのひとつが、10月1日にグランドオープン予定のDDD HOTELで、ここには客室の他に現代美術やストリートアートの展示をするギャラリーや、高級フレンチレストランなどが入っています。これらに脈略はなく、「好き」という理由だけで選ばれていることを伝えていきたいと思っています。また、近所に昆虫食を提供する飲食店も誘致するのですが、おそらく昆虫食が好きな人は10人に1人くらいのはずです(笑)。でも、そういうものを世の中に発信していくことがファッションにできることだと思っているんです。

どうせなら、良いボンボンでありたい 。
—事業を広げていく中で、クリエイターと接する機会もますます増えていると思いますが、それによって何か変化はありますか?
優秀なクリエイターたちは非常に面白いですし、彼らが出入りすることで社員もいきいきと働くようになりました。また、「いまどき問屋なんて」と相手にされていなかった取引先とも対等に話ができる関係性が築けてきました。当初考えていた、クリエイティブとコミュニティをつなぐことでビジネスを発展させるというところまではたどり着けておらず、そこは大きな課題ですが、少なくともいまは自分自身が楽しいし、人生が豊かになった気がします(笑)。はじめはビジネス目線でクリエイターを集めたいと思っていた節がありましたが、結局僕は彼らが大好きなんです(笑)。だから、時には採算度外視でクリエイターたちがやりたいことを応援したり、一緒になって考えたりしているんです。

シェアオフィスで開催されているファッションデザイナー・山縣良和さんによる「ここのがっこう」。国際的なファッションコンテストの入賞者を次々と輩出し、世界的に注目を集めている
—クリエイターのどんなところに惹かれるのですか?
僕は自分で人生を選んでいない、好きなものを見つけられていないというコンプレックスがあるので、彼らのように強く選んで行動をしている人たちへの憧れがあるんですね。例えば、先ほど話した昆虫食レストランのオーナーが最初に僕に話したのは、「武田さんが見たことがある虫はすべて食べたことがあります」ということでした。その時点でおかしいのですが(笑)、そこで彼はフードロスなどの社会問題を持ち出すわけでもなく、ただ虫が好きだと言うんです。これ以上の理由はないですし、この情熱こそが本人にとっての真実になっているんですよね。
—なんだか武田さんがパトロンのように見えてきました(笑)。
よくパトロン気質と言われるのですが(笑)、自分が身を削れるのであれば削れば良いと思っています。僕は、子どもの頃から「お前は後継ぎだから楽でいいよな」と言われてきたのですが、そういうヤツらに絶対負けたくないという思いで世界80カ国を旅したり、コネで入れる会社には就職しなかったところがあるんです。いま僕がさまざま事業をやれていることもある程度余裕があったり、物件という地の利があることが大きいのですが、だからこそチャレンジしないといけないと強く思っています。よく冗談で「SBSB」、しょせん(S)ボンボン(B)、されど(S)ボンボン(B)と言っているのですが(笑)、どうせなら良いボンボンでいたいと思っているんです。

街を巻き込みすぎない場づくり。
—クリエイターを中心としたコミュニティをつくってきた武田さんですが、街のコミュニティとの関わりについてはどう考えていますか?
僕らの事業を通じて、ファッション業界をはじめとする人たちが、横山町、馬喰町界隈に徐々に足を運んでくれるようになり、街の人たちからも少なからず注目されるようになりましたが、自分としては「街を巻き込みすぎない」ということを意識しています。まちづくりをしたいという意識は特になく、シンプルに自分が面白いと思うクリエイターを集めて、彼らが楽しめる場所をミニマルにつくっていきたいだけなんです。街という規模で考えると、どうしても合意形成が必要になってくることが多いし、その先に生まれるものは平均値以上にはならないと思っているんです。

日本橋横山町にあるログズビルの外観
—横山町、馬喰町界隈に続く衣料品問屋という産業自体を未来につないでいく意識はありますか?
それも正直ないんです。例えば、ここが和菓子で有名な街だとしたら、その味を未来に残す意義もあるかもしれませんが、問屋というのはあくまでもビジネス上の機能でしかなく、それは時代とともに変わるべきものですよね。でも、古めかしい小売店が残っているこの界隈の街並みを残していきたいという気持ちはあります。この辺りの問屋は、細長いビルの上層階を在庫置き場にしていたところが多いのですが、時代とともに在庫があまり必要なくなり、上の階が空いているビルも多いんです。うちもそれで上の階をシェアオフィスにしたわけですが、他の問屋さんのビルの上層階にもクリエイターを誘致して、空中都市につくり変えることができたら面白いですよね。以前にそれを提案してみたのですが、なかなか自ら手を挙げてくれる街の人がいないというのが現実なんです…。
—今後、この街でやっていきたいことをお聞かせください。
僕がこの街にコミットしているのは、ファッションをやっている理由と同じで、家業がここにあったことがすべてなんです。家業があるこの街を盛り上げたいと思って活動をしている過程で出会う人たちがいて、そういう人たちとのつながりを大切にしてきた結果、気づいたらホテルまでやることになっていました(笑)。もともとこの街に思い入れがあったわけではないのですが、いま自然とこういう状態になっているということが、僕の人生にとっても、会社にとっても良いことなんだろうと思っています。これからも街単位でこういうことをしたいということは特になくて、街の一角の数カ所だけで良いので、特殊なもの、他にないものをつくっていきたい。それらが連動していけば自然と人は集まってくるだろうし、僕らが目指しているのは所詮その程度のことなんです。その先のことは街の人たちがやってくれれば良いし、そういう人たちがたくさん現れてくることで、街は変わっていくのかなと思っています。

取材・文:原田優輝 撮影:岡村大輔
LOGS Inc.
日本橋横山町で創業した老舗問屋「丸太屋」の100%子会社として2016年に設立。帽子やストールなどの服飾雑貨を扱う問屋「ニューカネノ」や、ファッションに関わるクリエイターや企業が集まるシェアオフィスの運営を行い、セミナーなども開催している。洋服や服飾雑貨のOEM製造や、海外ブランドのライセンスビジネス、マーケティング支援なども行う。